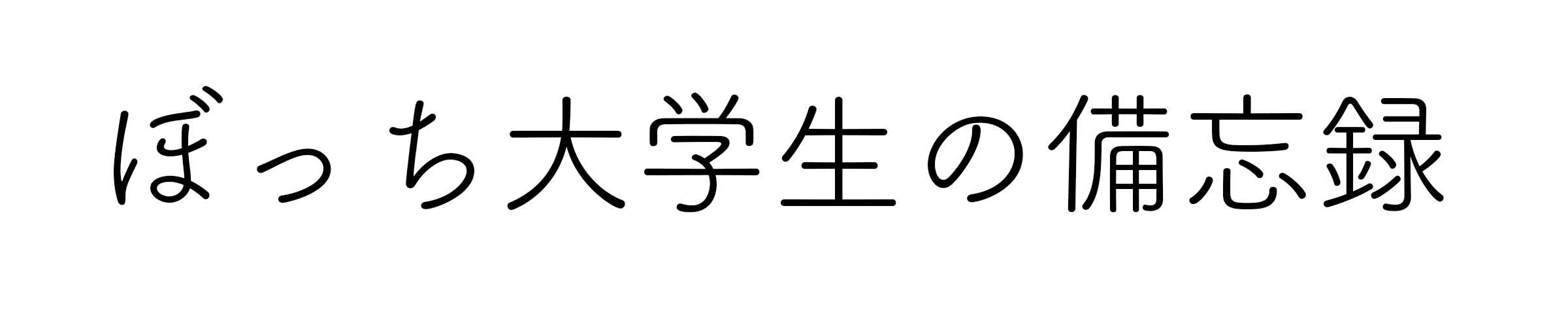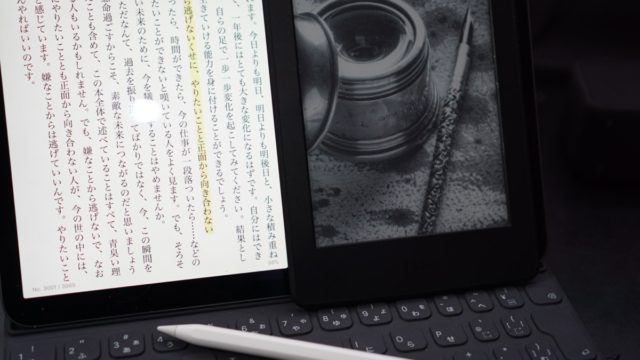本屋で見かけたこの「暗幕のゲルニカ」。心の奥底にある強烈なインパクトが蘇る。
小学校の頃観たゲルニカのレプリカだ。
実物大ではなかったが、自分が図工の授業で使うキャンバスとは比べ物にならないくらい大きく迫力があるレプリカが、資料室においてあった。
恐ろしい。
怖い。
そのキャンバスの中には濃密な負の感情が詰め込まれていた。
しかし、資料室脇の廊下を通るたびに観てしまう。
この絵から目を逸らしたらいけないのではないか。
鼻水をたらした小坊ながらにそう思いながら、卒業まで何度もその絵を視界の隅で捕らえ続けた。
この物語は主人公八神瑤子が「ゲルニカ」の魔力に魅せられる場面から始まる。
10才の時に、ニューヨーク現代美術館で遭遇したゲルニカ。
その中の左上に描かれた牛の眼差し。
彼女はその眼差しに引き寄せられるように、ピカソに魅せられ、ゲルニカに魅せられ、芸術の研究の道に進んでいく。
そして、この物語はピカソに魅せられたもう一人の女性を中心とした、二つの時間軸で描かれる。
一つは瑤子のいきる2000年代。
2001年9月11日。
MoMAのキュレーターとなった瑤子は最愛の夫を同時多発テロによって永遠に奪われてしまう。
それから二年後の2003年。
悲しみを抱えながらも瑤子はアートの力で戦争、テロと立ち向かおうと、ピカソの戦争と題した展示を企画するが、目玉となる「ゲルニカ」の貸し出しの交渉は難航を極めていた。
そんななか、アメリカはテロ支援国家としてイラクを名指しし、空爆を仕掛けると宣言。
その宣言が行われた国連のロビーには、いつもかけられているはずの空爆に苦しむ人々を描いたゲルニカのタペストリーはなく、あるのは暗幕だった。
もう一つの舞台は1930~40年代。
なんのつながりも内容に見える二つの時が「ゲルニカ」を通じて、絡み合っていく。
芸術家ピカソとその愛人ドラは共にスペインを祖国としているが、スペインでは内戦が起こり、二人はフランス・パリに住んでいた。
そんな中、ナチスによって行われたスペイン・ゲルニカへの空爆。
ピカソはこの攻撃に怒りを爆発させ、依頼されていたパリ万博の作品に「ゲルニカ」を制作する。
万博後もファシズムの勢いは増すばかりで、そのモチーフ故にファシストによって燃やされかねない「ゲルニカ」は、安全な場所を求めてアメリカへ「亡命」する。
その時ピカソは言う。
「スペインが真の民主主義を取り戻すまで、決してスペインには還さないでほしい」」p297
作中(現代)のクライマックスでは、ゲルニカに近いスペイン・バスク地方に潜伏するテロ組織がゲルニカは我々のものだと主張して、奪おうとする。
しかし、ゲルニカを人生をかけて研究してきた瑤子も、ピカソの横でゲルニカの制作過程をファインダーに納め続けたドラも、違う結論に至っていた。
ゲルニカは空爆に限らずこの世の全ての「戦争」に対するピカソの思いであると、そして、ゲルニカは誰のものでもなく私達人類全てのものであると。
ペンは剣よりも強し(The pen is mighter than the sword.)
と言う諺がある。
今は一見すると平和な世界に見えるかもしれないが、文庫本の解説の池上彰さんの言うように、のちの調査でイラクは化学兵器などは持っておらず、かえってイラクへの攻撃が結果的にISの台頭につながり、多くの命が奪われている。
その首謀者を殺害したと、アメリカが得意げに報じた。
どんなにアメリカが正当化しようとも、流血はまた新たな流血を呼ぶだけではないだろうか?何度でも報復として、第二・第三のISが出てくるのではないだろうか?
剣では争いは終わらないのではないだろうか?
本書の冒頭にピカソの一文が載っている。
芸術は、飾りではない。敵に立ち向かうための武器なのだ。(p6)
何もできないぼくは、その跡を何度でも焼き付けたい。対戦中抑圧されたヨーロッパの中で、どんな剣よりも強い絵筆を持った男の戦いを。
今日の独り言
調子に乗って、こんな物を書いてしまいました。